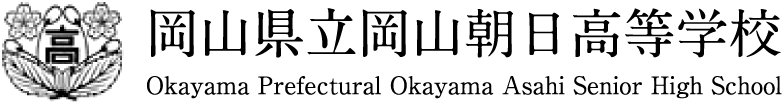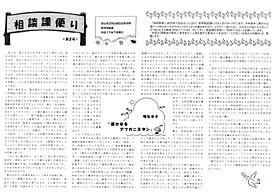『相談課便り』第2号
『相談課便り』第2号
『相談課便り』創刊号でお伝えしたとおり、教育相談課には9人のスタッフがいます。今年度中に発行する第2~4号の中でそのスタッフがエッセイを書きますので、どうぞご一読ください。みなさんが私たちスタッフの「知られざる素顔」を知ってくださり、そしてまた、相談課を気軽にご利用くださることを願っています。
今回は「国際派の明石」「気ままな一人旅を愛する長谷川」「本当はこころやさしいお母さんの柴田」が、登場します。
<平成17年7月発行>
遙かなるアフガニスタン
明石幸子
私には、夏になると必ず思い出す人物がいる。彼女の名は「マッハナーズ」、アフガニスタン出身の少女だ。彼女と私がルームメイトとしてひと夏をともに過ごしたのは、1982年、アメリカのニューヨーク州、ナイアガラフォールズにほど近いニューヨーク州立大学バッファロー校でのことであった。その年、日本の大学を卒業した私は、ロータリー財団の奨学生としてアメリカの大学院に入学するための準備に、3ヶ月の語学研修を当大学で受けていたのである。
栗色の巻き毛に、透き通るような肌、北欧出身かと見間違う彼女は、みんなの人気者であった。「(はっきりと)アフガニスタン一の富豪の娘」を自称する彼女の故国での生活は確かに豊かだったようだ。運転免許を取り立てだというのに、既に「自分専用」の自動車を4台も買ってもらっており、そのうち2台はベンツだそうだ。17歳の誕生日に父親から贈られた物らしい。「一体『家族』は何台の車を持っているのか」という質問には、しばらく数えていたようであるが、結局は“countless”(「数え切れない」)の返事が返ってきた。14歳の誕生日には、彼女へのプレゼントとして、父親が、「アフガニスタンで(今度は)1、2を争う」人気歌手を家に呼び、彼女のために特別のバースデーコンサートを開かせたそうである。その家というのも、4階建てでダンスホールらしきものまである、立派な洋館であった。「何不自由なく育った少女」というのが私の彼女への印象であった。
くるくると動き回り、よく笑い、常に男子学生に囲まれ、週末にはディスコで踊りを楽しむ彼女からは故郷を離れた寂しさは微塵も感じられなかった。いや私が気がつかなかったと言うべきかもしれない。そうあの日までは……。
熱があるから授業を休むという彼女を部屋に残し、私は一人で講義に参加した。ユニークな教授と、各国から集まった活気に満ちた学生、少人数で行う充実した授業。光溢れるカフェテリアでのたわいのないおしゃべり。緑のキャンパスを渡る風は夏のかおりを運んでいた。満ち足りた気持ちで部屋に帰った私を待っていたのは、同胞のアフガニスタン人の友達に囲まれて泣いているマッハナーズの姿であった。「マッハナーズはホームシックなのよ。母親に会いたいのよ。」彼女の従姉のリタが説明してくれた。「夏の研修が終われば一度アフガニスタンに帰ればいいじゃないの。そうすればお母さんに会えるよ」と励ますつもりで発した私の何気ない言葉は、その場の雰囲気を一気に変えてしまった。激しく泣き出すマッハナーズ、それを慰めるリタ。自分の言葉が引き起こした反応の大きさに戸惑う私がいた。しばらくしてやっと、彼女たちはぽつりぽつり説明してくれた。自分たちの渡米は「亡命」であったこと。二度とアフガニスタンの地へは帰れないことを覚悟して、国を出たこと。故国アフガニスタンでの激動の日々……。
1979年12月24日、年明けをあと数日に控えた厳寒のこの日、ソ連軍が国境を越えアフガニスタンの地に「侵攻」した。西側のメディアはデタント(「東西緊張緩和・雪解け」)の終わりを告げるこの事件を大きく報道した。(最もこの行動はソ連筋によると、「ソ連アフガン二国友好協定」に基づくアフガニスタン政府の「要請」に応じたためだということになっている。)首都カブールは完全にソ連軍の勢力下に入り、巻き返しをはかるムジャヒディーン(「自由の戦士たち」)との間に激しい内戦が勃発した。日々激化する戦闘。学校でもいつ爆発が起こるか分からない状態となった。戦火を逃れようと、隣国パキスタンに向かうため、難所のカイバー峠を越えようとする難民たち。ただマッハナーズの安全を脅かしたのは内戦による戦闘だけではなかった。「アフガニスタン一富豪」とされる彼女の父の資金を狙う各派からの誘拐工作も彼女をアメリカへと向かわせた大きな理由であったらしい。マッハナーズのアメリカへの道のりは簡単ではなかった。当時「非同盟諸国の盟主」と謳われながらも実際は親ソ路線を取るインドへ出国し、数カ国を経由してやっとアメリカへ着いた時には故国を離れてから二ヶ月が経っていたという。パスポートを発行してもらえたのは、ひとえに彼女の父の力によるところが大きかったのであろうが、同時に、そのような財界の要人が一家総出で亡命することを認めるほど政府も寛容ではなかったらしい。3歳の弟のパスポートは発行されず、当然母親は国を離れることはできなかった。アフガニスタンを発つときに母親と二度と会えないかもしれないことは「覚悟していた」と語ってくれた。
そんなマッハナーズの夢は、平和が戻ったアフガニスタンに、小児科医として帰ることであった。アフガニスタンでは乳児死亡率が高く5歳の誕生日を迎えられない子どもを「あちらこちらで知っている」らしい。(ちなみにユニセフの調査によると、1993年のアフガニスタンの乳児死亡率は1000人あたり165人である。)そんな子どもたちを救うことがマッハナーズの望みであった。
ひと夏の楽しい日々はあっという間に過ぎ去り、朝夕の空気がひんやりとし始めた9月、研修生たちは全米の大学に散らばっていった。私はユタ州に、マッハナーズはニューヨーク市に。頻繁に続いていた手紙のやりとりも、時の流れとともにいつの間にか途絶えてしまった。ちょうど、ソ連の侵攻を大きく伝えていたマスコミも、段々とその事件を扱うことが少なくなり、1989年2月「ジュネーブ合意」によりソ連が撤退したあとは、アフガニスタンのことはほとんど国際社会の意識から消えかかったように。
彼女のアフガニスタンに平和が戻る兆しはあまりない。ソ連の撤退後も、共産政権と反政府軍であるムジャヒディーンとの争いは続き、政権崩壊後は、今度はムジャヒディーン各派による勢力争いが激化した。それでもヨーロッパの民族闘争の陰に隠れ、国際社会から援助も注目も十分受けられず「国際社会の孤児」とまでいわれた1990年代のアフガニスタン。イスラム原理主義を掲げるタリバン政権が圧政を敷いた1990年代後半。アフガニスタンが再び国際社会の注目を浴びたのは皮肉にも2001年9月11日の「同時多発テロ」がきっかけであった。その後の国際社会の援助にもかかわらず、アフガニスタンにマッハナーズの望んだような平和が戻ったとは言い難い。
マッハナーズはどうしているのだろうか。今もアメリカの空のもと元気に暮らしているのだろうか。それとも、ひょっとしたら危険を覚悟でアフガニスタン再生に向けて故国に戻ったのであろうか。今となってはそれを確かめるすべもない。
あの夏の日々から既に20余年の歳月が流れ、楽しかった日々は、もう2度と戻ってはこない。マッハナーズとは二度と会うことはないかもしれない。ただ、それでも私の心から、あの輝く夏の日の思い出が消えることはないし、マッハナーズを忘れることも永遠にない。ひょっとしたら人間はそのような「輝ける日々」があるからこそ生きていけるのかもしれないし、そういう瞬間を求めて生きているのかもしれない。
とりあえず
長谷川雅之
今からもうずいぶん前、初めて北海道に行った時期は、今から考えれば無謀だったのかもしれないが、真冬だった。とりあえず服をたくさん着込んで、青森行きの夜行列車に乗り込んだ。
未明、目が覚め、外を見ると、列車は雪国を走っていた。おそらく、水田の広がる農村地帯なのだろうが、雪が大量に積もっていて、はっきりとはわからない。ただ、所々に家とわかる雪の盛り上がりがあって、なんとかどこかの集落が見えているのだとわかる程度だった。その景色は、どうみても音がしていない、無音の世界のように見えて、自分が生まれ育った所とは全く違う世界に来たのだと実感した。
しばらくして列車は青森駅に到着した。駅で肉まんと缶コーヒーを買い込み、函館に向かう連絡船に乗る。せっかく船に乗るのだからとデッキに出て、陸奥湾と青森市街を眺めながらの肉まんとしゃれこもうとしたけれど、あまりに寒いので船室に戻ることにする。後ろから、北島三郎の名曲を歌う人がいて、おそらくいつもの風景なんだろうと思った。
船では、なぜか地元の人とおぼしきお年寄りに話しかけられる。津軽弁なんだろうか、残念ながら何を言っているのかわからない。ただ、相当言いたいことがあるようだった。とりあえずにこにこしながら聞くことにした。熱弁が終わると、そのお年寄りはどこかに去っていった。彼は満足したようだ。いいことだ。
船が陸奥湾を出て津軽海峡にさしかかるあたりから、船体が大きく揺れ出す。気持ちが悪くなって船室で寝ることにする。4時間の船旅は意外と長く感じた。函館に着いたときには、疲れがどっと出た。
函館駅から市電に乗り換え、五稜郭を見に行く。ここは形が大事。上からみないと意味は無い。五稜郭からの帰り道を間違える。街中を延々と歩くはめになる。雪の積もる道は歩きにくい。
初日の宿は函館の北にある大沼という小さな街に求めた。宿のロビーには、延々と北の国からの主題歌が流れていた。当時私はこの話を知らず、なんなんだろうと思う。明朝、宿を出て跨線橋を渡り、駅に向かう。目の前に駒ヶ岳が見える。初めて北海道に来たのだと実感する。
あてもなくなんとなく北海道に来てしまい、どうしようかと思い、とりあえず札幌まで出た。さらにどうしようと思いながらも、ちょうど稚内行きが出る時間だったので、これに乗ることにした。昼食は駅弁のホタテ弁当。発車と同時に食べてしまう。札幌を出て、しばらくして車内から客がほとんど居なくなり、さらに旭川をすぎると、外の景色からも、ほとんど人の気配が無くなってしまう。北海道の原野を列車が進んでゆく。雪が積もった大平原の中に、ぽつんとある駅に停車する。駅と駅員さん以外、なにもない。雪原のはるか彼方に黒い森が見える。いったい誰が利用するんだろうか不思議である。その日は稚内で一泊。次の日には宗谷岬に行き、はるかサハリンを眺める。宗谷岬音頭らしき曲が流れ、妙に騒々しい。しかし周囲には民家の一軒もない。
稚内からはオホーツクを南下することにする。浜頓別という小さな町に泊まる。駅を出て宿まで、まだ昼間なのに吹雪で暗いなかを歩く。廃屋が連なる小道を抜けて街外れまでいくと、やっと遠くに小さな明かりを見ることができた。それが実は今宵の宿だった。木枠の窓を雪がたたき、ストーブの前で宿のご主人が出してくれた、温めたミルクを飲む。朝、牧場で絞ったミルクとのこと。
次の日、さらに南下する。どこに行っても本当に人が居ない。列車に乗っても同様。自分と、地元の人2~3人しか乗客が居ない。どうやらこの乗客は車掌さんと知り合いらしい。ほとんどの時間、乗客と雑談していた。私にはしきりにオレンジカードを勧めてきたが、買わなかった。
紋別、どこかで見た景色と出会う。
網走まで来る。駅前のラーメン屋で味噌ラーメンをすする。偶然、テレビで新しい岡山空港が開港したニュースをみる。妙な気分。ラーメン屋を出て刑務所見物。そのあと、バスに乗り、街外れの能取岬に向かう。バスを降り、雪原の中を岬の灯台に向かって歩く。能取岬の灯台は切り立った断崖の上にあった。数十メートルの断崖の下、オホーツクの海には水平線まで流氷が広がっていた。所々に流氷が切れ、海の水が見えている。真っ白な流氷と、真っ青な海の色とのコントラストが綺麗。その時、頭上をこえ、海に向かって遊覧のヘリコプターが飛んでゆく。
知床に寄り道をして、根室の街外れの納沙布岬へ。目の前は北方領土。ソ連の警備艇が浮かんでいる。そこから西に向かい、厚岸で一泊。もしソ連が攻めてきたら、網走と釧路を結ぶ線を防衛ラインとして自衛隊が戦う手はずだと、宿の人から聞く。もちろん、宿は釧路の東。その日は、宿から借りた湯たんぽを抱いて寝る。
北海道を発つ日は青函トンネルが開通して確か三日目だったと思う。開通直後、列車が立ち往生したりして、かなり混乱していた。もちろん、北海道では大きく取り上げられていた。予定より一本早い青森行きに乗り込み、待望の青函トンネルにさしかかる。入った瞬間、車内に歓声が上がる。ただ、入ってしまえばつまらない。仕方ないので寝る。ひとしきり眠って、おもむろに目が覚めるが、まだトンネルの中。やはり仕方ないので、もう一度寝る。トンネルを抜け、青森県にはいる。まだずいぶんと遠いところにいるのに、もうすっかり帰ってきてしまった感じがした。
親として思うこと
柴田みさえ
最近、小学校5年生になる娘が3歳の弟をしかっている場面をよく目にする。反抗期に入り、なかなか言うことを聞かない弟に腹が立つのであろう。興味深いのは娘のしかり方なのである。言葉遣いはもちろん、目つき、雰囲気が実に私に似ているのだ。私としては自分が娘をしかっている場面が録画されていて、それを見せられているようで、きまりが悪い。しかり方というのは遺伝するのか、と思うほどである。
実は私は自分の娘をほめることはほとんどない。生徒の言動に感心したり、ほめたりはよくするのであるが、自分の子供となると事情は違い、ほめることに対しての抵抗感が強くなる。よくよく思い出してみると、私自身あまりほめられて育っていない……のだ。私自身の父親も高校教員で、私も部活についていったり、家で採点しているのを見たりしていたが、自分の生徒のことは自慢げに話をするのに、娘である私に対しては厳しい指摘がくるだけだった。父親と同じように教員になった私に対して父は「10年しないと一人前ではない」と言い、10年たつと、「まだ辞めんのか」である。日本の平均寿命にだんだん近づいているのだから、そろそろその頑固さも年貢の納め時で、少しくらい「頑張っとるな」と言ってくれても良さそうなものだ。(しかし、そのような言葉が父の口から出るようになれば、いよいよ、認知症を疑わなければならないかもしれない。)
娘をなぜほめてやれないのか。1つにはやはり、子供に対する期待がある。これぐらいはできて欲しい。この程度は当たり前だ。と思ってしまう。自分自身も子供の頃、大してできもしなかったのだが、そんな昔のことは都合よく頭から抜けてしまう。さらに悪いことに、教員をしていると能力のある生徒をたくさん見るわけで、自然に合格平均点も上昇し、そんなわけで、自分の子供は常に赤点になってしまう。子供にしてみれば、ほめられないと達成感や自己肯定感が得られず不安になってしまうのであろう。私の娘に関して言えば、学校で起こった様々なことを報告する際にも、私がするであろうコメントには悲観的である。「お母さんはきっとくだらないと言うと思うけど……」とだいたい前置きがついてくる。これも、彼女の作り上げた自分を傷つけないための防衛本能なのかもしれない。報告を聞いた私のコメントもだいたい「くだらんなぁ」になってしまう。
先日、登校中の小学生が3人、路地の真ん中で頭をつきあわせて、何かを見入っているところに出くわした。何があるのだろうと目をやると、何のことはない、ぺちゃんこになった蛙を観察しているのである。小学生の好奇心に感心しつつ、これではなかなか小学校にたどり着かないなと最初はおもしろがっていたのだが、ふと、自分の子供だったら、笑ってはいられないだろうなと思った。開口一番、「何してんの!早く行きなさい!」と言うだろう。この場面で「そう、蛙がつぶれてるの?」と子供に共感できる親はそういないと思う。大多数の親にしてみれば、子供の好奇心より、学校に間に合って行かせることが大切になる。
しかし、よく考えてみると、近所のおじちゃん、おばちゃんを含め、子供を取り巻く世界のどこかに、あの日の私のように、子供達の好奇心に理解を示してくれる人がいるのではないかとも思う。楽観的すぎるかもしれないが、子供はそんな人たちに囲まれて、バランスを取りながら成長していくのかもしれない。悩んだ時も実は同じことで、様々な人がいろんなスタンスで見守ってくれている。自分が一番聞いて落ち着くアドバイスに、耳を傾け、心のバランスをとっていくのである。ただ、親というのは私の経験から話したように、なかなか客観的になれないこともあるので、感情的になってしまうこともある。親としては多分に子供のためを考えてのことなのだから、それは理解して欲しいのだが、でも理解できなければ、とことん言い合ってみるのもいいかもしれない。最終的に一番理解しようと努力してくれるのは、きっと親だと思う。実は先ほど登場した私の頑固親父もいつも「あの子はまた忙しいのか?」とよく母にチェックしている。意識しなくてもそうできるのだから、子供を心配する気持ちも遺伝するものなのかもしれない。