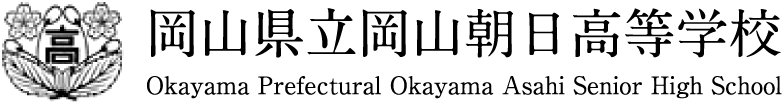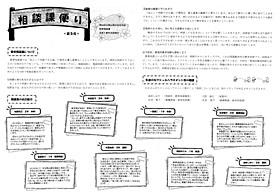『相談課便り』第5号
『相談課便り』第5号
- 教育相談課について
- 相談係の自己紹介
- 生徒のセクシャルハラストメント等の相談
- 学校医によるこころの健康相談
- スクール・カウンセラーによる相談
- 山の上の火
<平成18年5月発行>
山の上の火
池本しおり
教育相談の仕事に長く携わっていると「アドバイスが欲しくてやってきました」と言われる場面にしばしば出会います。そんなとき「この人は何かを模索していて、その答えを見つけるためにここへ来られたのだな」と思うことにしています。そこで間違っても「○○してみてはどうですか?」などと、相手の求めに誠実に応じて(?)簡単にアドバイスをしてしまうことだけは、極力避けたいと思っています。
またあるときには「先生何とかしてください」と言われることもあります。そんなときには「この人はどうしても何とか変えたい、何かをもっておられるのだな」と理解することにしています。同じく「この人の代わりに何とかしてあげよう」と、親切心を出して(?)張り切ったりしないようにしています。
そんな風に言うと職務怠慢だと叱られるかもしれません。「じゃあ、教育相談課の仕事って何なの?」と思われるかもしれません。いえ、そう思われる方が多いと思います。なぜなら、今まで「アドバイスが欲しくてやってきました」とか「先生何とかしてください」と言われる方に、本当にたくさん出会ってきたからです。つまり、「相談室というのはそういったことに対応してくれるところ」というイメージが少なからずあることの証左だと考えられるからです。
誤解のないようにお断りしておきますが、それでは全くアドバイスをしたり、課題解決のために手を貸したりしないかというと、そうではありません。情報提供のためのアドバイスは積極的にしています。たとえば、進路選択に関する情報提供などは最も代表的なものです。また、年度末には必ず「クラス替えの時に配慮してもらいたい」という相談を受けます。その訴えの正当性が感じられれば、「学年主任さんと相談して、できるだけ希望に添いたい」と答え、課題解決のために手を貸すことになります。しかし、私の行っている相談活動の全体からすると、そういったことはごく一部です。
朝日高校に転勤してくる前に勤めていた職場で、精神科医の青木省三先生にお世話になっていました。その青木先生がお書きになった『思春期こころのいる場所』は私の愛読書の一つです。この本の不思議なところは、「勉強しよう」というような貪欲な気持ちをいつのまにか忘れてしまい、本の中に自分も一緒に漂っているような気持ちにさせられることです。そして青木先生がいつもの穏やかな口調で、臨床家としてのさまざまな大切なことを、私に語りかけてくれているような錯覚をもってしまうのです。その中で、私が自分の相談活動において繰り返し肝に銘じている話があります。以下、その章「山の上の火」を紹介します。
エチオピアの古い民話に、青年とそれを支える人の関係について、とても示唆に富む話がある。ある時、アルハという貧しいわかものがハプトムという金持ちと賭をする。スルタ山の一番高い峰の上で、はだかで一晩中、立っていられたら畑をやるという賭である。アルハは、ものしりじいさんに相談した。そうすると、じいさんは次のように答えた。救いたまえ」。
「てつだってやろうかの。スルタ山から谷をへだててはんたいがわに、ひるまならよっくみえる高い岩があるからな。あしたのばんになったら、そうさな、お日さまがしずんだら、その岩の上で火をもやしてやろう。おまえのたっているところから、その火がよっくみえるはずじゃ。おまえは、一ばんじゅう、わしのもやす火をみとるんだよ。目をつぶったら、あかん。目をつぶったら、おまえはくらやみにつつまれてしまうからの。火をみつめながら、あったかい火のことを考えるんじゃ。それから、そこにすわって、おまえのために火をもやしつづける、このわしがいることを考えるんじゃ。そうすればの、夜風がどんなにつめたかろうが、おまえはだいじょうぶだ」
そして、アルハは遠くでちかちかしている火をみつめながら、一晩はだかで山のいただきにたつことができたのである。
( 『山の上の火』クーランダー、レスロー文、渡辺茂男訳、土方久功絵、岩波書店 )
この遠くの山で火をたくというところがいい。人と人との間には、そもそも深い谷間があるものなのだ。人は一人で生まれてきて、一人で死んでいく。自分の力で生きて行かなければならないし、決してその青年の代わりに誰かが生きてあげることもできない。親に護られていた状態から、いつの日か青年は覚悟をして一人で山の上に立つことが必要になる。
その時、まわりの人にできることは、心配しながら励ましながら見ていることだけである。ただその思いや気持ちが人を助けるのも真実である。遠くの山の家の火の暖かさは決して青年に伝わりはしないが、山の上で火を燃やす人の暖かい思いや祈りは伝わるのである。
そして、それが青年を支えるのだ。どのような技術や知識があったとしても、この思いや祈りがなければ、人が人を支えることはできないであろうと私は思う。ベテランになるということは、このようなじいさんになるという覚悟をすることでもある。
すぐに暖かい食事や毛布を届けるのでも、代わりに立ってやるのでもない。診察室から、病院から出て行く青年がこれから過ごすであろう暗闇の中でじっと立っていてくれることを、祈るような気持ちで見送るのである。その祈りが、青年にとって遠くの山の上の火となるように念じながら。
(『思春期こころのいる場所』(岩波書店)より抜粋 )
教師は「教えること」や「手を貸すこと」に慣れています。さらに悪いことには(?)「話すこと」にも慣れていて、ついつい自分が多くを語り、さっさとアドバイスを与えて「相手の役に立った」気になってしまいがちです。私が特に自戒していることは、過去に経験した同じような出来事(自分自身の経験や、他の生徒に関することも含め)を話して聞かせ、そのことによってアドバイスを与えることです。もちろんそのこと自体は悪いことではありませんし、その内容が相手の参考になることもあるでしょう。しかし、少なくとも私の経験からして、そのような経験談が有効に働くことは意外に少ないと感じています(これはあくまでも「教育相談活動において」という注釈つきですが)。
例えば、不登校の状態が続いている生徒の保護者にお目にかかるとします。お話の内容から「この子は情緒混乱型不登校だな」とか「無気力型だな」、あるいは、「不登校の初期の状態だな」とか「そろそろ動き始める頃かも?」などと自分なりの見立てをします。なぜなら、不登校にはいくつかのタイプがあり、時期によってその状態も違ってくるため、まわりの人の望ましいかかわり方も、そのタイプや時期で変えていく必要があるからです。このような考え方は数々の事例から導き出された「経験知」によるものであり、「その生徒をどのように理解し、対応していくべきか」という点において、大変役立つものです。それならそのパターンにのっとって、教科書通りのかかわりをしていけばいいかというと、それがそう簡単にはいかないのです。そういった経験知による「大きな流れ」を把握しながらも、やはりその人個人の資質や置かれている環境、不登校のきっかけや、それが続いている状態について、個別の事情を汲み取らなくては適切なかかわりも見えてこないからです。たくさんの相談にかかわっていれば、それだけ多くの事例に接することになるのですが、そうすればそうするほどむしろその多様性に気づき、その支援の在り方を模索することに慎重であろうとします。また、これら一連の理解や支援方針を含めて「見立て」であると考えています。
ここで相談の原点にかえり、「来談者の話にしっかり耳を傾ける」ということが大切になってきます。したがって、こちらが経験談を話したり、アドバイスを与えたりすることは、意外に有効ではないということになります。さらに先にそうしてしまったために、来談者が自分のことを話す機会が奪われたり、自分の中で試行錯誤しながら新しい道を探すことをしなくなってしまったら、それこそ本末転倒です。
「すぐに暖かい食事や毛布を届けるのでも、代わりに立ってやるのでもない」相談活動は、一見即効性が無く、何の役にも立っていないようにさえ思えます。また、こちら側にも忍耐が求められます。どうすればいいか聞かれてもそこで少し踏みとどまり、相手の考えるチャンスを奪わないよう、かといって突き放さないよう、一緒に考える姿勢を大切にします。そして相談が終わったときには、来談者が少し勇気をもち、何かに立ち向かっていってくれることを願います。それはまさに「山の上の火」をともし続けるじいさんの在り方そのものです。このじいさんは「ものしりじいさん」だからこそ、ほどよい距離をわきまえ、自分のなすべきことを知っているのでしょう。
「○○してはどうですか」と言いたくなったとき、私はこのじいさんのことを思い出します。また判断に困ったとき「じいさんなら何と言うだろうか」と考えることで、一呼吸つきます。このじいさんのような深い叡知を持ち合わせておらず、いつも迷ったり悩んだりしながら相談活動を続ける私にとって、「山の上の火」がはるかかなたに見えるとき、そのそばでじいさんが私のために祈ってくれていることを思います。その火は私に指針を与えてくれるものであると同時に、私を支え励ましてくれるものでもある、暖かい火なのです。